投資によって資産を増やしていくためには、的確な投資判断が求められます。そこで今回は、不動産投資や、最近人気が高まりつつある証券化された不動産への投資において用いられる基本的な判断指標、「LTV」について取り上げます。
不動産のLTVとは
LTVは「Loan to Value(ローン・トゥー・バリュー)」が正式名称で、「総資産有利子負債比率」と訳されます。
所有物件の資産価値に対する負債の割合(負債比率)を指し、物件全体から見る借入金の依存度を見極める指標です。実際の数値は「負債額 ÷ 物件価格」という数式で計算されます。
LTV = 負債額 ÷ 物件価格
投資家が意思決定をする際に使われる基準の一つで、LTVの数値が低い場合にはローリスクローリターン、対照的に数値が高い場合はハイリスクハイリターンの傾向があります。
不動産投資のLTVは80%以下が理想的
不動産投資の場面で使われるLTVは物件購入に要した借入額÷不動産価格という方法で算出されます。
LTV = 3000万円 ÷ 5000万円 = 0.6
上記のように5000万円の価値を持つ不動産を、3000万円の借り入れをして所有している場合のLTVは60%になります。
LTVの捉え方はケースバイケースですが、一般的に不動産投資におけるLTVは80%以下(頭金として20%以上支払っている状態)が理想的と言われており、LTVの数値が低い物件(自己資金(頭金)の投入割合が多い物件)の方が、金利が低いローンを組みやすい傾向にあります。
LTVの計算方法は時価と鑑定価格は数字の開きに注意
LTVの計算で使われる不動産価格には、「簿価評価」や「時価評価」といった異なる数値を用いた算出方法があります。
どの評価額を採用して計算するかによって、不動産価格が大きく異なる場合も出てきますので、注意が必要なポイントです。
会計帳簿に記録されている評価額のことです。購入時点の価格を指すこともあります。購入後の価値変動は考慮せずに評価する方法で、その物件を売却したときに損益が確定します。
時価評価
LTV算出時点での市場価格や評価額のことを指します。時価評価はその時点の資産の価値を正しく判断できるというメリットがあります。
簿価評価の場合、帳簿上の評価額や購入時の価格など、一定の額がLTV算出の際に用いられることになります。
一方、時価評価を採用する場合は、LTV算出時点での市場価格(時価)を用いることになります。実際の計算としては、簿価(不動産を取得した時の価格)に時価と簿価との差額を指す含み損益を加えてLTVを算出することになります。
簿価LTV = 有利子負債 ÷ 帳簿価格 × 100
時価LTV = 有利子負債 ÷ (帳簿価格+含み損益) × 100
時価評価と少し異なるのが、期末など一定のタイミングの鑑定評価額(帳簿価格+含み損益)を用いるケースです。
この場合、簿価(実際に不動産を取得した時の価格)に加えて考慮する「含み損益」は、鑑定評価額と簿価の差額となります。
鑑定評価額LTV = 有利子負債 ÷ (帳簿価格+含み損益) × 100
※時価評価の場合と計算式は同じですが、含み損益の算出方法が異なります。
時価評価額や期末などに発表される鑑定評価額を用いて計算した場合には、市場環境によっては物件取得時の価格と算出に用いる評価額に大きな開きが出ることがあります。
リスクへの備えがわかるLTVテストとは
不動産投資においては、不動産の額に対するローン残高の割合を指すことが多いLTV。
このLTVを応用して、実際にローンを返済できる可能性や、リスクに対する蓄えが適切かどうかを図るのがLTVテストです。
LTVテストを行う際には、[返済予定のローン残高 ÷ 不動産評価額]という式で算出された数値を用います。
この不動産の評価額は、不動産鑑定書のほかに、下記のような価格を変動させる可能性がある要素を考慮したうえで決められます。
返済予定のローン残高 ÷ 不動産評価額
- 立地条件
- 施設の用途
- 建物のグレード
- 不動産の管理状況
- 権利関係(所有権、借地権など)
- 入居テナントの質
不動産投資信託(REIT)などの投資商品では、LTVテストの結果、不動産ごとに定められている目標格付けの基準を下回った場合には、投資家への配当が制限されることがあります。
LTVをベースとした投資物件の選び方
LTVは不動産投資における負債比率のことを指し、物件全体から見る借入金の依存度を見極める指標です。
一般的には、LTVの数値が低い(借入金への依存度が低い)方が金利も抑えられる傾向にありますが、LTVの数値が高いからといって、必ずしも投資に適していない物件というわけではありません。
LTVが高い物件によく見られるパターンが、短期での資産売却を視野に入れているケースです。このような場合、自己資金の資金効率が高くなることがあります。
借入金への依存度が高いというリスクは伴いますが、不動産投資商品の場合は、高値で対象物件が売却された際には高額な配当金を手にできるというメリットが考えられるからです。
LTVの数値は、あくまでも投資プランを検討する際の参考指標の一つです。証券化された商品などの場合には、商品を取り扱っているファンドや企業の運用実績をみると各運用主体の投資傾向が見えてくることも多いので、LTVの数値と併せて参考にすると良いかもしれません。
LTVが用いられる代表的な金融商品
LTVは、不動産投資やREITへの投資にあたり、投資の優劣を見極める基準の一つとして広く使われています。ここでは、LTVが用いられることが多い代表的な商品と、その特徴をご紹介します。
不動産投資信託(J-REIT)
投資家から集めた資金で複数のオフィス・店舗ビル、共同住宅等を購入し、その運用や売却によって得られた収益を投資家に分配する商品です。証券取引所に上場されているため、流動性が高い点が特徴です。
少額での不動産投資や個人では手を出しにくい高額物件に対する投資ができる点や、不動産投資法人による運用が行われるため、購入後の手間が少ない点から人気を集めていますが、市場環境の変化により投資商品に価格変動リスクがある点や上場廃止といったリスクを背負う可能性もある点が懸念点として挙げられます。
クラウドファンディングによる不動産投資
少額でも実際に物件を保有してみたい方に支持を集めている商品の一つとして、クラウドファンディングによる不動産投資商品があります。
複数の物件を1つのファンドとして資産運用が行われるREITに対し、ロードスターキャピタル株式会社が組成するエクイティ型クラウドファンディングによる不動産投資商品では、ある1つの不動産を管理・運用していくことが前提となっています。
エクイティ型クラウドファンディングとは、投資家からクラウドファンディングによって集めた資金で不動産信託受益権を購入し、対象物件の運用によって得られる賃料収入や売却利益を元に、投資家に配当として返還する仕組みです。
不動産信託受益権とは、不動産をいったん信託銀行等に信託した上で、その不動産から発生する経済的利益を受け取る権利のことを指し、不動産の運用が行われる場合に広く用いられています。

エクイティ型クラウドファンディングの投資商品は、不動産の賃料収入や売却利益が配当資金の原資になるため、貸付先からの返済分(元本+確定利息)を原資として配当を行う貸付型クラウドファンディングよりも原資の額が不確定で、ハイリスクハイリターンな傾向にあると言われています。
高額で不動産が売却された場合には高い配当を受けることができる一方、不動産価格が低下してしまった場合には損失を被る可能性もあるので、投資を検討する物件の状況や、運用会社の実績などを元にして投資すべきかどうかを考える必要があります。

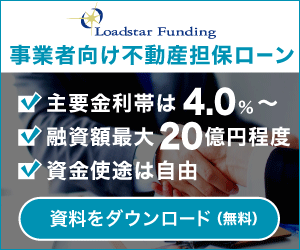



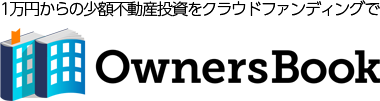
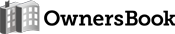
0 件