AMとPM。不動産業界では、この単語を聞いて午前/午後と同じくらい、もしかしたらそれ以上に当たり前のように想起される言葉として、「アセットマネジメント(AM)」/「プロパティマネジメント(PM)」があります。
アセットマネジメントが投資用資産のポートフォリオ全体の収益を最大化する業務のことを指すのに対し、プロパティマネジメントは個別不動産の物理的な管理・運用業務を指し、特に収益性の確保・向上を目指した業務をいうこともあります。
この投稿では、プロパティマネジメント業務の概要について解説いたします。
業務内容
プロパティマネジメント業務の対象は主にオフィスビル、商業ビルや賃貸住宅で、駐車場や事業用収益物件等を扱うこともあります。業務内容は大きく運用業務と管理業務に分けられます。
運用業務は不動産の運用計画の立案、賃料の設定、テナントの募集・契約等で、管理業務は建物や設備の維持・保全、予算・収支の管理等です。以下で詳しく見ていきましょう。
≪運用業務≫
リーシング/テナント管理業務
オーナーに代わり、建物を賃借するテナントの管理業務一連を行います。具体的にはマーケット調査から適正賃料等の条件を見極め、テナント誘致を行うとともに審査を行い、物件の稼働率の向上を目指します。また、賃貸借契約の管理、賃料管理等の他、テナントからのクレーム対応も行います。
≪管理業務≫
メンテナンス業務
良好な環境と建物の資産価値の維持は、良質なメンテナンス業務によってもたらされます。そのため、プロパティマネジメント会社は日常的な巡回点検、定期的な法定点検・自主点検、清掃業務等によって建物の保守管理および営繕を行います。このハード面の管理が、入居者や来訪者の印象や満足度といったソフト面にも寄与します。
アカウント業務
賃料等の入出金管理や月次毎の賃借人に対する請求書の発行、各種費用の支払い手続き、年度末の会計報告や税務処理等は想像以上に手間のかかる業務です。プロパティマネジメント会社はオーナーに代わってこれらの業務を行います。
コンストラクションマネジメント業務
建物や設備は年々さまざまな不具合や劣化が生じるため、適切な時期に改修・修繕工事を行い手をかけることが必要です。また、中規模から大規模なリニューアル工事を行うには計画性が必要で、プロパティマネジメント会社は有用性や遵法性を考えながら、オーナーの意向に沿った適切な管理計画の立案、工事計画の策定、工事業者の選定、工事業者の施工内容等の精査、工事監理等を行います。
プロパティマネジメント業務は多岐にわたるため上記のように区分して把握されることが多いですが、最も重要なのは、不動産のオーナーとテナントのつなぎ役として、総合的に不動産から得られる収益を最適化することであると考えられています。
なぜプロパティマネジメントが大切なのか、またこの分野における今後のIT化の余地については次回以降で解説いたします。

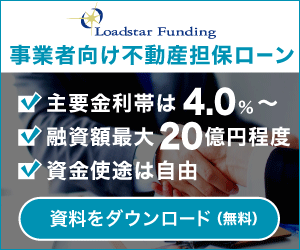



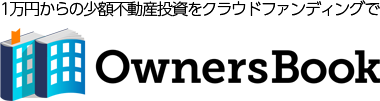
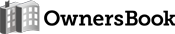
0 件