不動産投資を行うにあたり、金融機関からの融資を受けることはほぼ必須です。その際、金融機関は通常、資金の返済を担保するために、その不動産に対して「抵当権」を設定し、登記します。抵当権にはマイホーム購入時に住宅ローンを借りる際に一般的に設定されるような抵当権(以下、本記事では根抵当権と区別するために「普通抵当権」と記載します。)と、根抵当権の2種類があります。
今回は、普通抵当権と根抵当権の違いと、根抵当権の元本確定や根抵当権設定者、根抵当権の譲渡など、不動産を運用する上で必要な知識について、詳しく解説していきます。
普通抵当権と根抵当権
金融機関が住宅ローンなど特定の融資をする際に、担保として土地や建物に普通抵当権を設定し、登記した場合、金融機関は借り手がローンの返済ができなくなったときに、土地や建物を強制的に売却し、その代金から融資したお金を回収することが可能です。
そのため、土地や建物の価値がある限り、借り手の業績や資金繰りが悪化した場合にも、貸し手は担保不動産の処分によってローンを回収することが可能となります。
借り手が返済期限までに特定の融資(融資①)の返済を完了すると、融資①の担保として設定した普通抵当権も同時に消滅します(「抵当権の附従性」といいます。)ので、融資①の普通抵当権の抹消登記手続きを行います。
次に同じ金融機関から別の融資(融資②)を受けるケースを考えてみます。融資②を担保するため、同じ土地や建物に普通抵当権を設定する場合、新たに抵当権を設定し、登記する必要が生じます。
この場合、前の融資(融資①)の担保のために設定した普通抵当権の登記を抹消せずに、融資②の担保として流用することはできません。そして、当然、融資②に対して設定した普通抵当権についても、別の融資の返済が完了したら抹消登記手続きを行う必要があります。
このように、融資を受けるたびに設定登記を行い、返済が完了したら抹消登記するということを繰り返していては、手間も費用もかかってしまいます。
そこで、一定の範囲内の不特定の債権(「銀行取引による債権」などと表現します。)について、決められた金額内であれば、一度の設定で、繰り返し行われる融資などの取引を担保できる権利があります。
このように、一定の範囲内の不特定の債権を、決められた金額内において担保するためにある不動産に設定された抵当権のことを、根抵当権(「ねていとうけん」と読みます。)といいます。また、その根抵当権を行使することができる金額の限度額のことを極度額といいます。
不動産投資においては、普通抵当権と根抵当権、どちらも設定が可能です。ただ、例えばリフォームをするために追加で同一の金融機関から融資を受ける必要があるかもしれないといった場合には根抵当権を設定するのが便利かと思われます。
根抵当権の元本確定とは
ここからは、根抵当権を知る上で、合わせて知っておきたい知識を解説していきます。まずは、普通抵当権にはない考え方である「元本確定」についてです。
先ほど述べたとおり、根抵当権は、極度額の範囲内であれば、一度の設定で、その後行われる融資などの取引を何件でも担保できるというものでした。
ところが、何らかの理由で、今後の取引についてはこの根抵当権の対象外としたいという事情が発生することがあります(ある融資の返済が滞り、不動産を強制的に売却して代金から融資したお金を回収したい場合や、借り手と後述の物上保証人との関係性に変化が生じた場合など)。
このとき、その時点で未返済額がいくら残っているかを明確にすることを、根抵当権の「元本確定」といいます。
元本確定とは、その根抵当権で担保される債権額(債務額)を確定させることです。元本確定以降に発生する債権は担保されなくなり、元本確定の時点で存在した債権(債務)が返済されると、根抵当権は消滅します。また、元本確定は一度行うと、撤回することができません。すなわち、元本確定した時点で、根抵当権は普通抵当権と同様の担保権になると言えます。
根抵当権者と根抵当権設定者の違い
続いては、根抵当権者と根抵当権設定者について解説します。
根抵当権者
登記された根抵当権により、融資したお金を担保できている人のこと。通常は融資における貸し手(債権者)です。
根抵当権設定者
根抵当権が設定・登記された不動産の所有者であり、根抵当権者に担保として提供している人のこと。融資における借り手(債務者)がこれに当たることが多いです。
また、根抵当権を含む抵当権は債務者自身の財産ではなく、第三者の財産に対して設定されることもあります。この場合、根抵当権設定者に当たるのは第三者であり、借金をしているわけではないが、他人の借金のための責任を自分の所有物によって保証しているということから、「物上保証人」とも呼ばれます。
根抵当権の譲渡の2つの方法
続いて、根抵当権の譲渡について解説していきます。根抵当権の譲渡とは、根抵当権者が、根抵当権をほかの人や機関に譲り渡すことです。
譲渡の方法は、「全部譲渡」、「分割譲渡」、「一部譲渡」の3通りあります。
全部譲渡
根抵当権のすべてを譲受人に譲渡することです。全部譲渡すると、譲渡人の債権はこの根抵当権により担保されなくなり、譲受人の債権が担保されることとなります。
分割譲渡
根抵当権を2つに分割し、その一方を他人に譲り渡すことです。分割した根抵当権はそれぞれの根抵当権者ごとに独立したものとなるため、それぞれの極度額を決める必要があり(合計すると元の根抵当権の極度額)、譲渡人、譲受人はそれぞれの極度額に応じた自己の債権が担保されることとなります。
一部譲渡
根抵当権を分割せず、譲渡人と譲受人が根抵当権を共有する形になるように、根抵当権の一部を譲り渡すことです。根抵当権の極度額はかわらず、譲渡人と譲受人はそれぞれの債権額の割合又は譲渡人と譲受人が取り決めた割合に応じて自己の債権が担保されることとなります。
なお、根抵当権の譲渡の際には、根抵当権設定者は必ず譲渡に承諾するかどうか確認されます。その理由としては、根抵当権は不特定の債権を担保するものであるため、設定者を無視して譲渡されてしてしまうと、設定者が予測していなかった不利益を被る可能性担保をつけるつもりがなかった債務に担保がついてしまう可能性)があるからです。
但し、元本確定後については、担保される債権が特定されるため、抵当権と同様の処分をすることができ、その際には根抵当権設定者の承諾は不要です。
また、根抵当権で担保されたローンを、担保付の状態のまま譲り渡したい場合には、元本確定により担保される債権を特定する必要があります。
根抵当権設定の具体例
5,000万円のマンションを購入して不動産投資を行う際に、3,000万円の不動産投資ローンを組むとします。
この際、この3,000万円の債務に対する担保として5,000万円のマンションに普通抵当権を設定することが可能ですが、追加でリフォームをしたい場合など新たに2,000万円の融資を受ける際、たとえこのマンションに担保になっている価値以外に2,000万円の価値が残っていたとしても(担保余力といいます。)、この2,000万円の債務に対して、再度抵当権を設定する必要が生じてしまいます。
これに対して、マンションに極度額5,000万円の根抵当権を設定した場合を考えます。
この場合、購入資金として当初に3,000万円を借りた後、例えば、購入後のリフォーム用に500万円、2年後の大規模修繕費用に300万円を借りることとなった場合にも、新に抵当権を設定する必要がありません。(※)
※実際に貸してくれるかどうかは貸付人との契約に拠りますので、その点はご留意ください。
但し、普通抵当権又は根抵当権の設定を登記する際には、普通抵当権であれば債権額、根抵当権であれば極度額に応じた登録免許税が必要となります。また、普通抵当権であれば貸付元本に加えて2年分の利息及び遅延損害金が担保される一方、根抵当権では極度額を超える金額は担保されません。
上記のケースで普通抵当権・根抵当権のどちらを選択するのか、根抵当権とする場合に極度額をいくらにするのかは、リフォームや修繕が発生する可能性やその際に必要となる金額を踏まえて慎重に検討し、貸付人と交渉する必要があります。
不動産運用の上で欠かせない根抵当権
根抵当権についての理解を深めていただけたかと思います。お金の借り入れや返済を何度も行う際、普通抵当権に比べ根抵当権は登記に関するかなりの手間を省くことができ、不動産運用の際に非常に心強いものとなります。皆さんもぜひ根抵当権を活用し、不動産運用の効率化を図ってみてはいかがでしょうか。
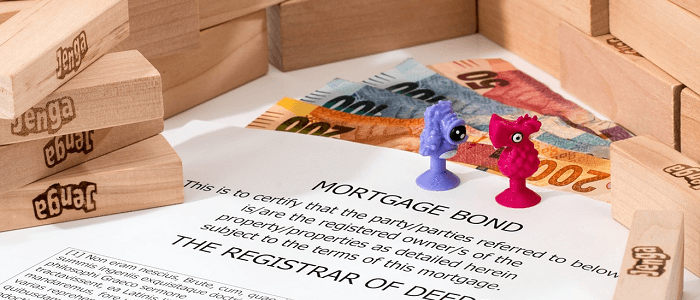
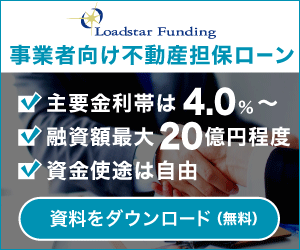




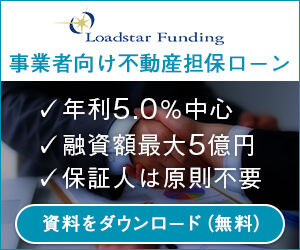
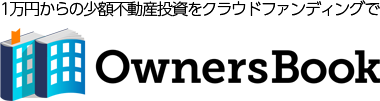
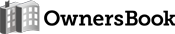
0 件