不動産の購入には莫大な資金が必要になりそうですが、不動産のオーナーになり利益の追求をするメリットにはどのようなことがあるのでしょうか?
ここでは実際にアパートやマンションを購入しそのオーナーとして家賃収入を得る不動産投資のメリットについて考えてみたいと思います。
不動産投資のメリット①:売却益や家賃上昇の可能性がある
物価が上がった場合には、購入した物件そのものの価値が上がる可能性もあり、売却すれば利益が出て、また家賃も上昇する可能性があります。
不動産投資のメリット②:毎月、安定した賃料収入が見込める
安定した賃料収入が見込める場合、将来的に働くことが出来なくなった場合などのことを考えると賃料収入を年金として考えることも可能です。ローンを組んでいれば返済に充てることも可能ですし、返済が終わっていれば年金受給者にとっては年金の足しになりゆとりある老後生活の備えになりそうです。
不動産投資のメリット③:生命保険の役割を果たす場合も
マイホームを購入される際にローンを組んだ方はご存知かと思いますが、民間のほとんどの金融機関では住宅ローンなどの多額のお金を借りる際、団体信用生命保険への加入が義務付けられ、契約者に保険がおりる事由が生じた場合には残りのローンが免除されます。最近では投資目的で購入する不動産を担保に組むことの出来るローンで、団体信用生命保険が付保されるものもありますので、調べてみる価値はありそうです。
お金を受け取る生命保険とは違い、ローンがなくなれば家族に不動産を財産として残せる可能性もありますね。
不動産投資のメリット④:節税対策が可能
不動産投資で得た収入にはもちろん税金が掛かってきますが、ローン金利などが必要経費として認められているようですので、申告することで所得税や住民税の節税も可能のようです。税理士の方に確認してみる価値がありそうです。
このように、昨今年金制度や終身雇用制度が危ぶまれるなか、将来の不安を拭うために、将来に渡って継続した安定収入が図れる不動産投資をはじめる方が増えているとも聞きます。
また、せっかく家を購入したけど転勤になってしまった!もしかしたらこれは大家さんになるチャンス?手放す前に家を貸すことを選択肢に入れてみるのも一つの手かもしれません。その際には、賃貸可能か住宅ローンの条件もご確認ください。


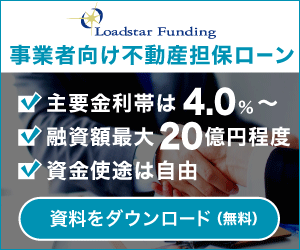

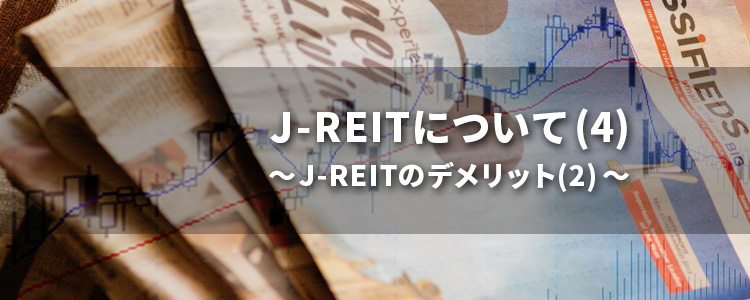
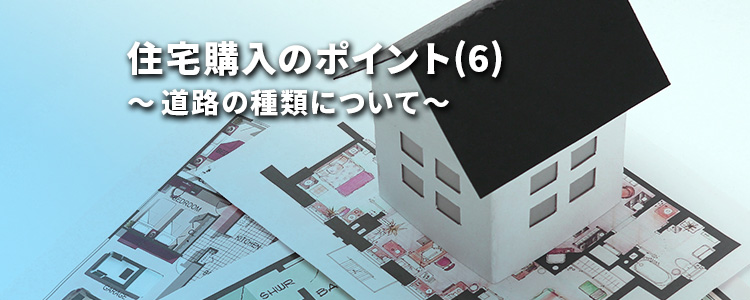
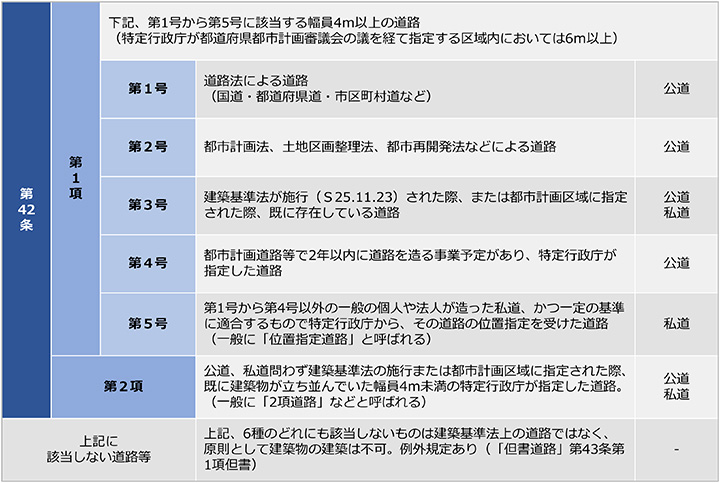
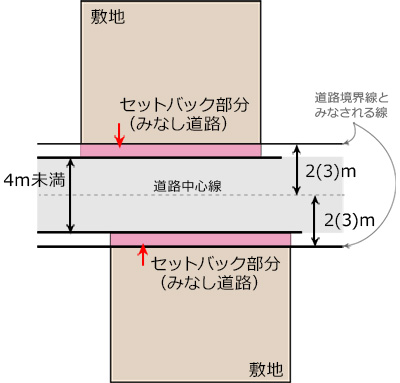
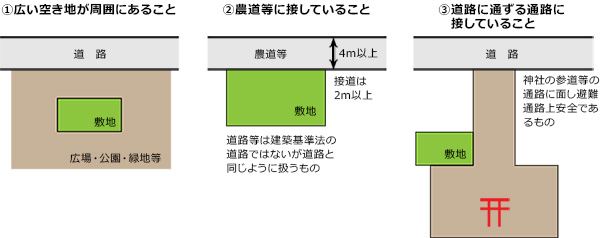
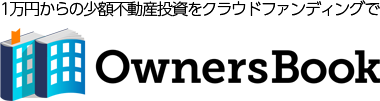
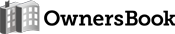
0 件