2016年1月に導入が決定された、日本銀行によるマイナス金利政策。不動産業界も大きな影響を受けるといわれていましたが、その中でも、住宅ローン金利はマイホーム購入に強く関係することもあり、注目を集めました。それでは、住宅ローン金利はマイナス金利政策の実施でどのように変動したのでしょうか?
今回は、マイナス金利政策が住宅ローンに与えている影響と今後の見通しについて、銀行ローンとフラット35を念頭に解説いたします。
住宅ローン金利のその後
住宅ローンは主に「固定金利型」「固定金利(期間)選択型」「変動金利型」という金利タイプに分かれます。それぞれについてみていきましょう。
【固定金利型】マイナス金利導入後、低下。
固定金利は、通常10年物の国債利回りを基準に決定されています。マイナス金利政策の導入により10年物国債の価格が上昇、結果として10年物国債の金利は低下しました。これに連動する形で、固定金利型住宅ローンの金利も下がっています。
例)大手都市銀行の借入期間20年超35年以内のローン。
2015年10月時点:2.16% ⇒ 2016年10月時点:1.46%
【変動金利】マイナス金利導入後もあまり変化なし。
変動金利は通常短期プライムレートに連動しますが、マイナス金利導入後も短期プライムレートは据え置かれており、変動金利型の住宅ローンの金利はマイナス金利導入後もあまり下がっていないのが現状です。
マイナス金利と短期プライムレートの関係については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
・関連記事:マイナス金利と短期プライムレート
【固定金利(期間)選択型】マイナス金利導入後、固定期間が長いものほど低下。
一定の固定金利期間(2年、3年、5年、10年等様々)が経過したのち、変動金利または固定金利(期間)選択型を選べるタイプの住宅ローンです。現状一番多く利用されているのは10年型のようです。このタイプの場合、金利の基準となるのは、固定期間が2~3年の場合は短期プライムレート、10年固定の場合は10年物の国債利回りです。そのため、現状では固定期間が長いものほどマイナス金利の恩恵を受けられている、といえそうです。
住宅ローンの借り替え申込者が急増
金利引き下げを受けて住宅ローンの借り替え申込者が急増し、銀行や不動産販売会社等で行われている借り替え相談会は多くの来場者で賑わっているといいます。
住宅ローンは借入額が大きいことから、金利がコンマ数ポイント(0.x%)変わるだけで返済額に数百万円の差が生じる場合もあります。現在借りているローンとの金利差や借入残高、返済期間等を確認したうえで、借り替え手数料等の諸費用を考慮してなおローン費用を節約できそうな場合には、借り替えを検討すると良いと考えられます。
今後の住宅ローン金利の見通しは?
住宅ローン金利の今後の見通しはどうなるのでしょうか?
日銀は、2016年9月の金融政策決定会合で金融緩和策をさらに強化することを明らかにしました。マイナス金利の適用及び長期国債の買入れの組み合わせ、長短金利操作のための新型オペレーションの導入等々が明らかにされましたが、これにより住宅ローン金利の行方を推測してみましょう。
【固定金利型】および【固定金利(期間)選択型】
10年物国債の利回りは現在マイナスで推移していることが多く、これが0%程度に維持されることになった場合、金利は今後わずかに上昇したとしても大きく変動することは予想し難い、すなわち今後も低い水準に留まる、と予想されます。
【変動金利型】
現状、マイナス金利の恩恵をあまり受けていないものの、今後もマイナス金利政策が継続されていくことにより、しばらくは現状のままで推移していくと予想されます。
住宅ローンを組むにあたり、住宅ローン金利の基準に影響を与える政策や金利市場の動向には、引き続き注視していきたいところです。

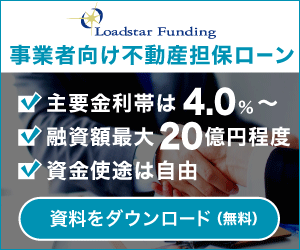



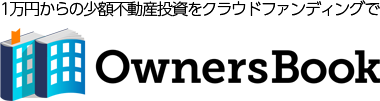
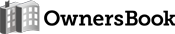
0 件